たとえば、地域で何かを始めようとする。
新しい取り組み。少しだけリスクがある。
でもやってみたい。
その瞬間、聞こえてくるのは、こんな言葉たちだ。
「過去に似たことやったけど、うまくいかなかったんだよね」
「前例は?実績は?稟議通る?」
「せめて来年度からにできない?」
こうして、新しい挑戦は“なんとなく”見送られる。悪意はない。誰かが止めたわけでもない。
でも、確実に“その空気”はある。
あえて言うなら、「失敗しないことを目的にする文化」が、そこにはある。
それは、組織が歳をとった証でもある。地域が“いい子”でいようとする結果でもある。
そして、この空気が続く限り・・まちは、変われない。
というより、変わらなくて済むようなふりをして、静かに沈んでいく。
「失敗しない」が最優先の世界
気づけば、会議の言葉がやたらと慎重になる。
「関係各所との調整を踏まえて…」「実現可能性を慎重に見極めながら…」「一部、反対の声も想定されるので…」「時期尚早では…」
そして最終的に出てくるのは、あの決まり文句。
「今回は、もう少し様子を見ましょうか」
見た目は穏やか、語尾は丁寧。
でも実質的には、「やらない」ことが決まった。
これが続くと、どうなるか。
誰も挑戦しない。
誰も責任を取りたがらない。
誰も新しい話を持ち込まなくなる。
そして、挑戦そのものが「空気を読まない行為」として、そっと排除されていく。
ここまで読んで、「まさかそんなこと、うちでは」と思った方。
いえ、あるんです。普通に。
というより、だいたいの組織にはどこにでもあるんです。
『失敗の本質』が暴いた、日本的組織の「敗北のパターン」
1984年に刊行された『失敗の本質』は、旧日本軍という“世界有数の巨大組織”が、なぜ敗れたのかを、戦略ではなく組織文化の視点から冷徹に分析した一冊である。
で、結論は端的に言うとこうだった。
「日本軍は、失敗を受け入れられなかった。だから学べなかった。だから変われなかった。だから、負けた」
つまりこういうことだ。
ミッドウェーで大敗したとき、大本営はこう言った。
「敵の空母2隻を沈め、我が方の損害は空母1隻にとどまる」・・もちろん、嘘である。実際には主力空母4隻を一気に失っていた。
問題は、「嘘をついた」ことではない。「失敗を組織的に共有しなかった」ことにある。
これは、敗北の事実を覆い隠すだけでなく、次の意思決定にも大きな影響を及ぼす。
なにせ、正確な情報が“上”に届かないから、戦略の立て直しもできない。
「指導者は間違えない」「組織は無謬である」
そんな信仰が、現場の声を封じ、判断ミスを連鎖させた。
で、何が起きたか?
同じ失敗を、何度も何度も繰り返した。
学ばない組織に、未来はなかった。それが、旧日本軍の“敗北の本質”だった。
そして残念ながら、その文化は形を変えて、今も日本社会のあちこちに息づいている。
この“空気”が、地域にも流れている
たとえば、地域でも・・
- 失敗した事業の報告書が“形だけ”で終わる自治体
- 誰も読み返さないワークショップの議事録
- 住民からの意見が「貴重なご意見として承りました」で止まる
- 挑戦を恐れて、結果的に「縮小運営」しか選べない地元行事
思い当たる節、ないだろうか?
これらはすべて、「失敗を恐れるあまり、動かない」ことの副産物である。
そして、「今あることを守る」ことが、「未来を捨てる」ことに直結している場合がある、という不都合な真実。
地域が抱える課題の多くは、変化を恐れる組織文化に起因する。
失敗はしていない。
でも、進んでもいない。
それって、本当に“うまくいっている”って言えるだろうか?
「失敗は財産」と本気で言えるまちへ
では、どうすればこの空気を変えられるのか。大切にしたいのは、「失敗を責めない」ではなく、「失敗を活かす」という視点。
うまくいかなかったプロジェクトこそ、振り返る価値がある。誰も来なかったイベント。応募が集まらなかった企画。住民に反発された取り組み。
そこに、地域の“今”が詰まっている。
何が響かなかったのか。どう見られていたのか。伝え方のどこにズレがあったのか。
それを、責任追及ではなく、「学びの素材」として扱う。“次の挑戦のヒント”として蓄積する。それが、「挑戦が続く地域」の条件になり、その条件があれば、地域にはチャレンジしたい人たちが集まってくるだろう。
「失敗しないこと」が失敗につながる
地域において、挑戦とは、制度よりも先に「空気」で決まる。
やってみてもいい。うまくいかなくても、またやってみればいい。それをちゃんと評価しよう。
そう言える空気があるかどうか。
失敗を受け止める余白があって、やわらかく包むようなまち。そんな“懐の深さ”が、いま求められている。










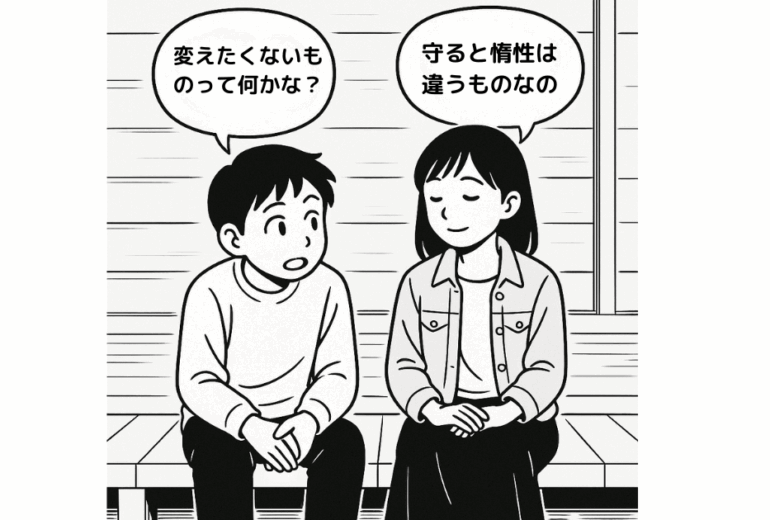
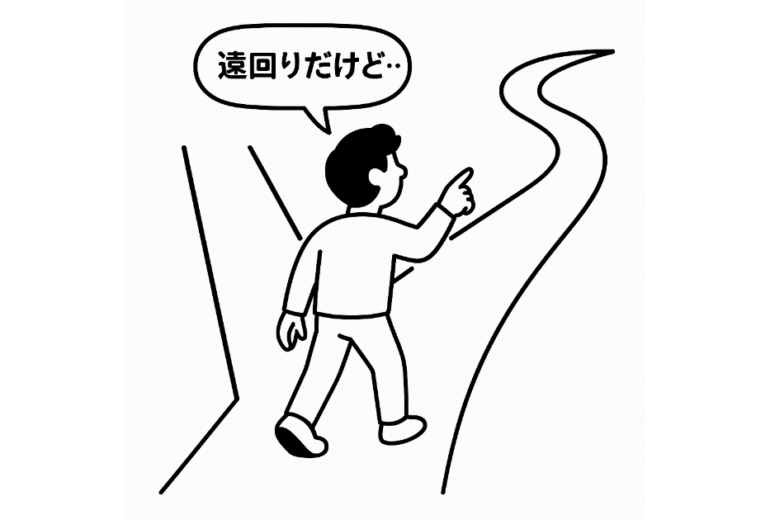



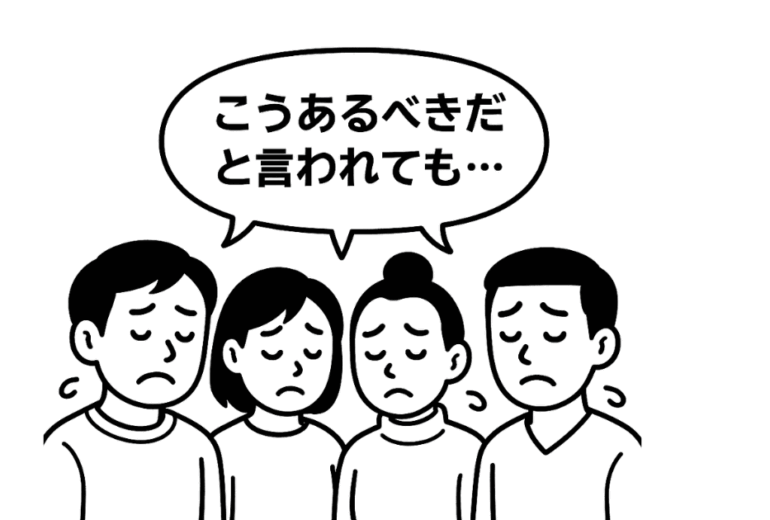


コメント