にっちもさっちもいかない・・そんな言葉があります。
物事がどうにもこうにも動かなくなったとき、前にも後ろにも進めず、出口が見えなくなったとき、日本語では「にっちもさっちもいかない」と言います。
語源には諸説ありますが、意味するところははっきりしています。どちらの選択肢も取りにくく、身動きが取れない状態です。
そして2026年1月現在の日本の金融・財政を見ていると、この言葉が妙にしっくりきます。
金利を上げれば、国債費と財政負担が重くなる。金利を下げれば、円安やインフレ圧力が再燃しかねない。利下げも難しい。利上げも難しい。
市場関係者の言葉を借りなくても、「にっちもさっちもいかない局面」に入っていることは、多くの方が肌で感じ始めているのではないでしょうか。
長期金利上昇と、よくある誤解
2026年に入り、日本の長期金利は上昇基調にあります。10年国債利回りは1.3%台まで上昇し、2011年以来の水準となりました。これについて、「高市首相の積極財政を市場が嫌気している」という論調を目にする機会が増えています。
しかし、ここは慎重に見る必要があります。
現時点で確認できる事実から言えば、長期金利上昇の主因は、日本固有の政治要因ではありません。1)米国で利下げ観測が後退し、長期金利が高止まりしていること 2)グローバルに「金利のある世界」へ戻りつつあること 3)日銀が大規模緩和から徐々に距離を取りつつあること
これらは、日本だけでなく先進国共通の流れです。
そのうえで日本については、1)国債残高がGDP比約260%と、主要国で最も大きいこと 2)日銀が国債発行残高の約半分を保有しており、需給構造が特殊であること 3)YCC終了後、「誰が最後の買い手なのか」が見えにくくなっていること といった構造的な要因が、あらためて意識され始めました。
高市政権の誕生は、その流れの中で市場の仮説を補強する「材料」として意識されている、それくらいの距離感が、もっとも正確だと考えられます。つまり、長期金利の上昇は「高市政権が原因」というより、「低金利を前提にした10年間の終わりが、可視化され始めた」と捉えるべきでしょう。
そしてその10年間こそが、アベノミクスでした。
異次元緩和によって金利をゼロ近辺に固定し、財政にも企業にも家計にも、極めて有利な環境をつくりました。その猶予期間を、私たちはどう使ったのか。何を変え、何を変えられなかったのか。
長期金利が動き始めた今、その問いから逃れることはできません。
もう「成功だったか失敗だったか」ではなく、「どう受け止めるか」
だからこそ、今問われているのは、「アベノミクスは成功だったか、失敗だったか」という、すでに擦り切れた二択ではありません。むしろ、「アベノミクスで買った時間を、私たちはどう使い、今それをどう受け止めるのか」という問いについて、冷静に考えるべきでしょう。
長期金利が上昇し、金融政策が「万能の時間稼ぎ装置」ではなくなりつつある今、答え合わせのフェーズに入ったと考えるのが自然です。
ここでは、「アベノミクス」とは何だったのかを切り口に、答え合わせしようと思います。
1.「アベノミクス」とは何だったのか
教科書的な整理は、最小限にとどめたいと思います。アベノミクスは次の「三本の矢」で説明されてきました。
- 大胆な金融緩和
- 機動的な財政政策
- 成長戦略
このうち、現実に最も大きな影響を与えたのは、間違いなく異次元の金融緩和でした。日銀が国債を大量に購入し、長期金利を極端に抑え込み、2%インフレを目標設定として、マイナス金利、YCCの導入・・
その結果、日本は「成長率は高くないが、とにかく金利は低い」という、きわめて特殊な均衡状態に入りました。
言い換えれば、構造問題に踏み込めない代わりに、「時間」をお金で買った10年だったと言えます。
2.「炭鉱のカナリア」が鳴き始めたという感覚
長期金利の上昇自体は、異常ではありません。問題は、それが何を前提に揺れているかです。
市場の一部では、今の状況を「炭鉱のカナリアが反応し始めた」と表現しています。これは「日本がすぐ危機に陥る」という意味ではありません。むしろ、低金利を前提にした財政・社会構造が、もはや当然ではなくなりつつあるというサインに近いものです。
まだ致命的ではありません。しかし、無視できる段階は明らかに過ぎつつあります。
3.高市政権は「アベノミクスの第4章」なのか
高市政権は、政策スタンスとして拡張的な財政運営を志向していると受け止められています。ただし、ここで重要なのは、市場は「誰が首相か」を評価しているのではないという点です。市場が見ているのは、この先、財政規律が強まる可能性は高いのか、それとも拡張的な前提が続くのかという方向感であり、高市政権はその判断材料の一つにすぎません。
原因ではなく、増幅要因(触媒)。この位置づけを誤ると、議論はすぐに歪んでしまいます。
4.答え合わせとして見えてくるもの
ここ10年を、「時間の使い方」という視点で振り返ると、避けられない問いが浮かびます。
① 構造改革は、どこまで進んだのか
低金利という猶予期間は、産業構造転換・地方分散・社会保障と税制の再設計・インフラと行政サービスの再編に使われるはずでした。
しかし現実には、成長戦略は部分最適にとどまりました。たとえば、政府は「第四次産業革命」や「Society5.0」といったビジョンを掲げましたが、デジタル化の遅れは2020年のコロナ禍で露呈しました。行政手続きのオンライン化率は主要国で最低水準、マイナンバーカードの普及も時間がかかり、結局、給付では郵送申請が殺到しました。産業構造の転換より、既存産業の延命に予算が使われる場面が多かったのです。
また、地方創生は補助金依存から抜けきれませんでした。地方創生交付金は2014年度以降、累計で数兆円規模が投じられましたが、多くの自治体では「補助金が出るから事業をつくる」構造が定着し、終了後も自走できるモデルは限られました。人口減少に歯止めはかからず、東京一極集中はむしろ加速しました。」
そして、社会保障改革は先送りされたまま。後期高齢者の医療費窓口負担を2割に引き上げる改革は2022年にようやく実施されましたが、対象は一定所得以上に限定され、抜本改革には至りませんでした。年金の受給開始年齢引き上げ議論も、選択的繰り下げの範囲拡大にとどまり、制度の持続可能性を根本から問い直す改革は避けられ続けました。
その結果として、どうなったのか?
成長しにくい構造は温存されたまま、国と日銀のバランスシートだけが膨らんだという姿が見えてきます。
② ゼロ金利前提のインフラと人口減少
地方では、さらに切実な課題が顕在化しています。人口が減っても、道路も学校も上下水道も、フルセットで残ります。
たとえば、人口3万人の地方都市では、ピーク時5万人だった時代に整備した上下水道を維持し続けなければなりません。利用者は減り、料金収入は先細りますが、配管の更新には億単位の費用がかかります。低金利だから、起債でつなぐ。それが可能だった時代は、確実に終わりつつあります。金利が1%上がれば、100億円の借入に対する年間利払いは1億円増えます。金利が上がれば、当然のことながら、新規借入の負担は増え、借り換えのたびに利払いが重くなる。
縮小する社会を、大きな器のまま維持し続けることの難しさが、否応なく可視化されていくのです。
5.「ポジティブ・シュリンク」という別解
この、答え合わせは、誰かを断罪するためにあるのではありません。大事なのは、これからの10年を、また「時間を買う10年」にしてしまうのか、それとも前提を受け止め直す10年にできるのか、という選択です。
4DeeRが関心を持ち、実践しようとしているのは、ローカルからの別解づくりです。
まず、すべてを守る前提を手放す必要があります。現状維持ではいられないことだけは確かなのです。「切り捨て」ではなく、「選択と集中」として設計し直します。
例えば・・小さくても密度の高い公共と暮らしを設計します。図書館、公民館、子育て支援センターを別々に維持するのではなく、一つの「まちの居場所」に統合します。延床面積は半分でも、使われる時間と人の密度は2倍になる。そんな再編が、すでに一部の自治体で始まっています。
そして、補助金より、人と関係性に投資します。移住者を呼び込むために移住支援金を出すより、地域で新しい仕事をつくろうとする人を伴走支援します。箱モノより、人が育つ土壌に予算を回します。
「増やす成長」から「縮めながら深める成長」へ。
その転換を、現場から具体化していくことが求められています。
終わりに・・「にっちもさっちもいかない」から先へ
長期金利の上昇も、高市政権のスタートも、ニュースとしては一瞬で流れきて消費されていきます。しかしその背後で、低金利を前提にした時代の終わりという、かなり大きな地殻変動が進んでいます。
ここから先を、「あのときがターニングポイントだったね」と振り返れるのか。それとも、「結局、また時間だけが過ぎた」と言うことになるのか・・
この局面を、単なる停滞と捉えるのか。
それとも、前提を書き換える契機と捉えるのか。
株式会社4DeeRとしては、後者の可能性に目を向け、ローカルからの実践を積み重ねていきたいと考えています。






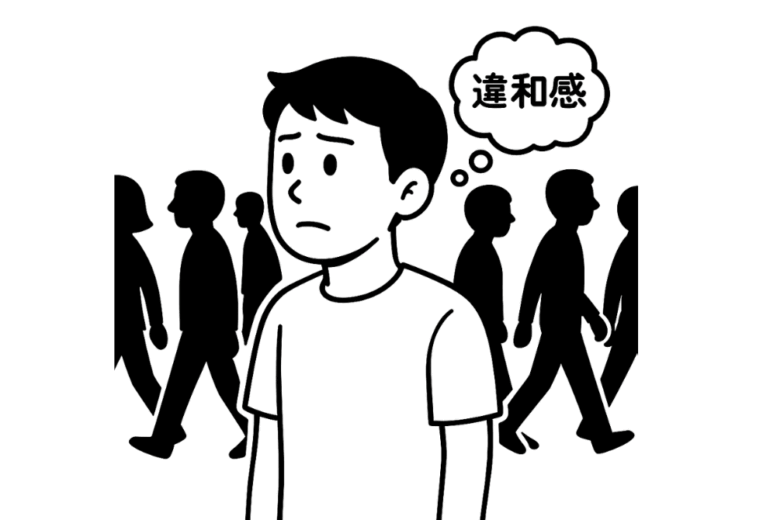

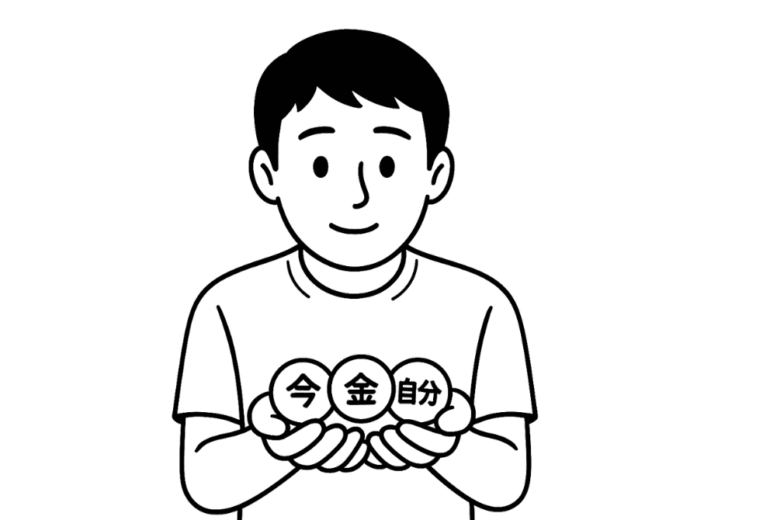


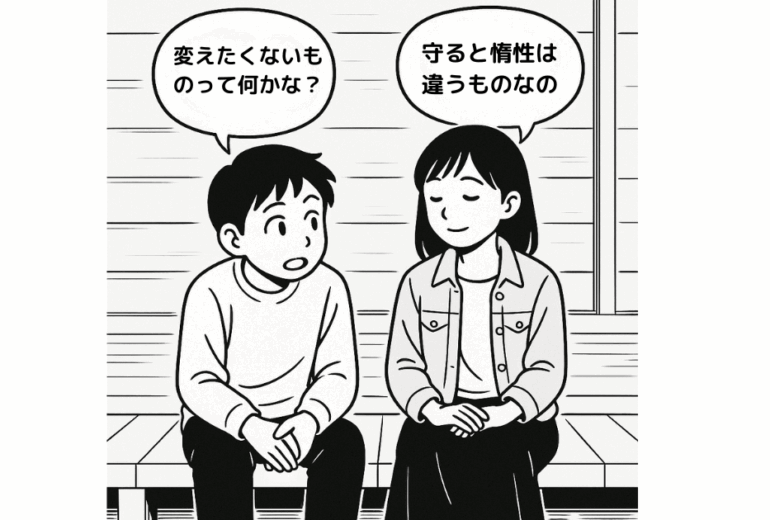





コメント