近年、日本の地方自治体は急速な人口減少に直面し、移住者の獲得をめぐる競争が激化しています。各自治体が移住促進のための補助金や住環境の整備を行っていますが、人口の絶対数が減少する中で、移住者の奪い合いが続けば、結果的に増える自治体と減る自治体が生まれる「ゼロサムゲーム」となる可能性が高くなります。また、移住者に対する手厚い補助金政策は、一時的に効果を上げるかもしれませんが、財政負担が大きく、長期的には持続不可能となる恐れもあります。
このような状況下で、自治体が持続可能な発展を遂げるためには、「住民票を登録する移住者」に依存するのではなく、関係人口や地域外の活動人口の増加を重視する新たな視点が求められます。つまり、住民としての定住はしなくても、地域と多様な形で関わる人々を増やすことで、地域経済の活性化や社会的ネットワークの強化が図られ、結果として自治体の持続可能性が高まると考えられます。本稿では、「関係人口」、「活動人口」を軸に移住を前提としない持続可能な地域づくりを考察します。
1. 移住者獲得競争はいずれ限界に
現在、多くの自治体が移住者を獲得するために、住宅補助、移住支援金、子育て支援などの施策を導入しています。しかし、こうした政策には以下のような課題があります。
(1) ゼロサムゲームによる地域間競争
移住者の奪い合いが発生し、一部の自治体が移住者を増やしたとしても、他の自治体がその分減るだけで、全国的な人口減少という根本的な問題の解決にはならないのが実情です。結果的に、移住者を呼び込める自治体とそうでない自治体の格差が拡大することになります。
(2) 移住定着の難しさ
多額の補助金を受けて移住した人でも、定住し続けるとは限らず、数年で別の自治体へ移動するケースもあるのが現実です。移住者の満足度や定住意欲を高めるためには、仕事や地域コミュニティへの馴染みやすさが不可欠であり、単なる金銭的支援だけでは不十分です。
(3) 財政負担の増大
移住支援金や住宅補助が財政を圧迫し、将来的に持続可能な政策とは言えません。特に税収が限られる地方自治体にとっては、移住者を増やすことで短期的な効果はあるものの、長期的には大きな負担となる可能性があります。
2. 移住に依存しない地域活性化の必要性
移住者獲得競争の課題を踏まえると、地方自治体が持続的に発展するためには、移住者の確保だけに頼らない戦略が必要となります。その中で注目されるのが「関係人口」や「活動人口」の拡大です。
(1) 人口減少社会に適した持続可能な地域づくり
日本全体の人口減少が進む中で、すべての自治体が移住者を増やすことは現実的ではありません。一方で、地域と関わる人々を増やすことにより、定住人口の減少による影響を補完し、地域活性化を図ることができます。
(2) 地域経済への貢献
関係人口や活動人口が増えれば、地域での消費活動が促進されます。ワーケーションや副業・兼業などを通じて、都市部の人材が地域に関与する機会が増え、地域内のビジネスやサービスが活性化する可能性があります。
(3) 社会的ネットワークの強化
地域と外部の人々とのつながりが強化されることで、新たなアイデアや技術が地域に持ち込まれ、外部の企業や団体との連携が生まれることで、地域の発展につながる可能性が高まります。
3. 関係人口、活動人口とは
近年、人口減少と都市への人口集中が深刻化する中で、地方の持続可能性をいかに保つかが大きな社会課題となっています。このような状況を受けて、定住人口の増加だけに頼らず、地域と多様に関わる人々の存在に注目が集まり、誕生したのが「関係人口」と「活動人口」という概念です。
「関係人口」という言葉は、雑誌『ソトコト』編集長の指出一正(さしで・かずまさ)氏によって提唱されたとされています。指出氏は、2004年の新潟県中越地震の際、支援活動などを通じて地域と深く関わりながらも、現地に住んでいない人々の存在に強く関心を抱きました。このような「住んでいないけれど地域に継続的に関わる人々」のあり方に注目し、関係人口という言葉を広めていったのです。その後、明治大学農学部教授の小田切徳美氏などの有識者や総務省もこの概念を取り上げ、政策的にも活用されるようになりました。特に、2018年度に総務省が開始した「関係人口創出・拡大事業」によって、関係人口という言葉が制度として正式に位置づけられ、全国の自治体に広く普及する契機となりました。関係人口の定義は、国土交通省によると「移住した『定住人口』でもなく、観光に来た『交流人口』でもない、地域や地域の人々と多様に関わる者」とされています。
一方、「活動人口」という言葉は、コミュニティデザイナーである山崎亮氏によって提唱されました。山崎氏は、地域における住民の能動的な参画や、地域外の人材による継続的な関与を通じて、まちづくりを進めることの重要性を訴えてきました。彼が参画した地域計画の議論などの場で、「活動人口」という言葉が用いられるようになったのは2010年代後半とされ、2019年3月8日に国土交通省が開催した「国土審議会計画推進部会 住み続けられる国土専門委員会」においても、山崎氏が活動人口という言葉を用いて説明を行っています。活動人口とは、国土交通省の定義によれば「経済活動とは異なる価値基準を含め、何らかの形で地域の社会・経済活動に関心を持って継続的に関わる者」を指します。つまり、地域で日常的に何らかの「活動」を行っている人々の総体であり、住民票を持っているかどうかを問わない広義の概念です。
これらの概念は、人口減少社会における「人の関わりの質」に着目し、地域との新たな関係性のあり方を示すものとして重要な意味を持っています。「定住」を前提としないこれらの概念は、関わりの多様性を尊重し、地域に継続的な活力をもたらす新しい関係構築の可能性を示唆しています。
4. 「能動的な関係人口」とは何か、なぜ必要か
能動的な関係人口とは
「能動的な関係人口」とは、地域外に居住しながらも、地域の課題解決や価値創造に対して主体的・継続的に関わる人々を指します。いわば「地域外の活動人口」とも言える存在であり、「定住はしないけれど、暮らしや仕事の一部を地域と共有する人々」で、4DeeRによる造語です。従来の「関係人口」や「活動人口」の枠組みでは捉えきれなかった、「地域に積極的に関与し、行動する外部人材」の存在に光を当てたものです。能動的な関係人口は、住民票を持たずとも、主体的にプロジェクトや課題解決に携わる人々であり、意志を持って地域の持続性に寄与する点が特徴で、下記のような効果が期待できます。
- 移住者に依存しない地域づくりを可能にする 定住者が減少する一方で、「そこに住まなくても関わり続ける人」が増えれば、地域の人口減に伴う社会的・経済的な空洞化を防ぐことができます。
- 多様なスキルとネットワークの流入 都市部で専門性を磨いた人材が、能動的な関係人口として地域に関与することで、新たな知見や技術、人的ネットワークが地域にもたらされ、イノベーションの種になります。
- 地域内外の連携を強化する 地域住民と地域外の担い手が協働することによって、課題解決が加速し、地域づくりが「自助・共助」から「協働・共創」へと進化していきます。
- 定住に至る可能性も含んだ関係 能動的な関係人口は、将来的な移住・定住の候補者であると同時に、定住せずとも地域に長期的に貢献できる存在でもあります。その柔軟性が、人口減少社会において極めて重要です。
地域の持続可能性を高めるためには、移住を前提とせず、地域外に住む人々とも多様な関係を築き、共に地域づくりを進めていくことが重要です。今後、自治体や地域団体が能動的な関係人口の受け入れ環境を整え、積極的に関与できる仕組みを構築することで地域の持続可能性の向上が見込めます。地域との関わり方が多様化する中で、「住まなくても地域に貢献できる」という新たな価値観が広がることが、地方創生の新しい未来を切り拓く鍵となるでしょう。










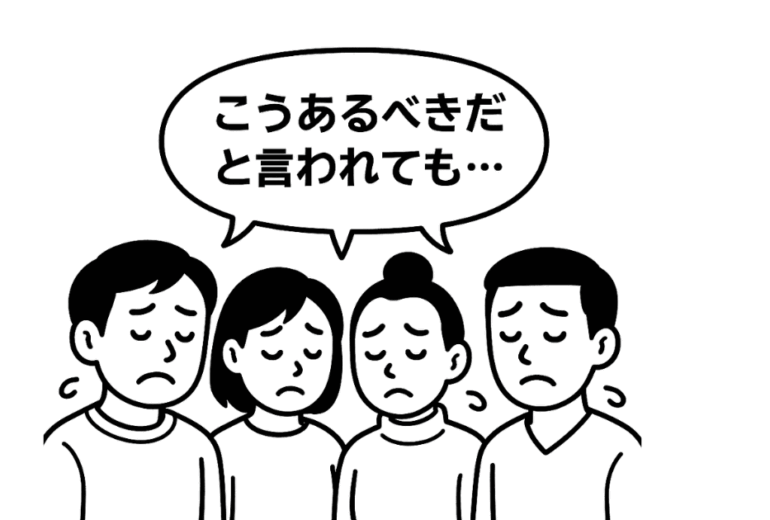







コメント