「これって、本当にやる意味あるのかな?」そんな違和感を覚えたことはありませんか?何かを良くするために始めたはずのことが、いつの間にか「やること自体」が目的になってしまっている・・・
この“目的と手段の転移(転倒)”は、民間でも行政でも起こりがちな現象ですが、特に地方行政の現場において、深刻な影響を及ぼすことがあります。
目的と手段の転移とは?
本来は「目的を達成するための手段」でしかなかったものが、時間の経過や慣習の中で、それ自体が目的になってしまう現象です。
たとえば──
・子どもの生きる力を育てるはずだった教育が、「テストの点を上げること」になってしまう 、地域課題を解決するための補助金が、「補助金を獲得すること」自体にすり替わってしまう
こうした構造的な問題は、私たちの生活に見えない形で大きな影響を及ぼしています。
行政現場における「補助金の目的化」
地域の課題を解決するための支援として設けられた補助金。ところが、その補助金に合わせて事業をつくる、報告書のために活動を形だけ整える……といった場面は少なくありません。
補助金がなければできないのではなく、補助金の枠組みに合わせないとできないという状況。 これは、もはや手段が目的になってしまっている状態です。その結果、住民のニーズや現場の創造性が抑え込まれ、地域本来の可能性が見えづらくなってしまいます。
政治の現場でも・・・「当選」がゴールでいいの?
本来、政治家は社会課題の解決や政策実現のために立候補するはずです。しかし、当選や再選が優先されるようになると、「政治家であり続けること」自体が目的になってしまう。
その結果、本音より無難な言葉が選ばれる 、ビジョンより人気取りが重視される 、政策実現よりポストの確保が優先される
こうした政治の“空洞化”は、地方にも静かに広がっています。
なぜ、目的と手段はすり替わってしまうのか?
- ・形式主義の定着:やり方が固定化すると、形を守ることが第一に。
- ・数値評価への依存:KPIや点数など「測れるもの」が目的になりやすい。
- ・組織的惰性:「前からやっているから」という安心感。
地方の現場でも「やることはやっているはずなのに、なぜか前に進まない」ことがあるとしたら、それは“目的と手段の転移”が起きているサインかもしれません。
じゃあ、どうすればいいのか?
- 立ち止まって問い直す こと。「そもそも、なぜそれをやっているのか?」 事業やプロジェクトごとに、定期的な振り返りの場を設けることが必要です。評価軸を見直す点数や数値だけでなく、住民の変化や声、空気感、関係性といった質的な成果にも目を向ける必要があります。思いを言語化する 関係者が「何を大事にしたいか」を言葉にして共有することで、軸がぶれにくくなります。
問いを忘れない地域であるために
“本当に大事なこと”は、数値化しにくいし、すぐには目に見えないことも多い。でも、「この地域の未来をどうしたいのか」「なぜこの取り組みを始めたのか」。 その“問い”を忘れないことが、地域を前に進める力になるはずです。手段の先に、本来の目的があるかどうか。 その視点を、これからの地域づくりの現場にこそ大切にしていきたいと思います。











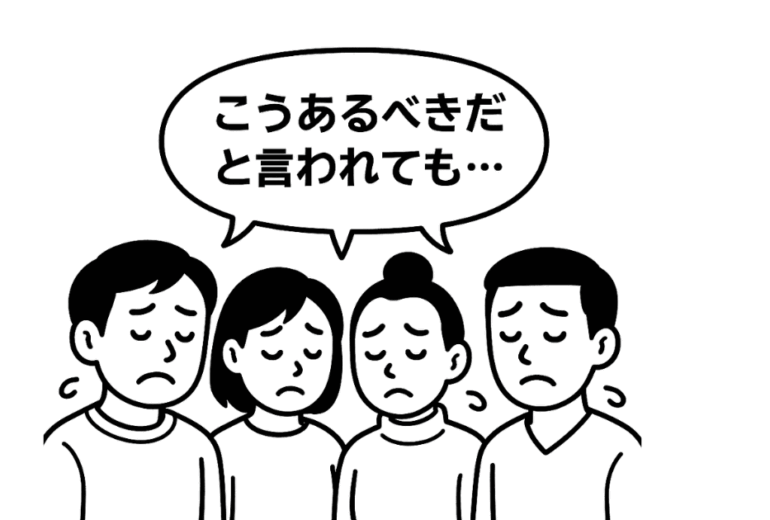

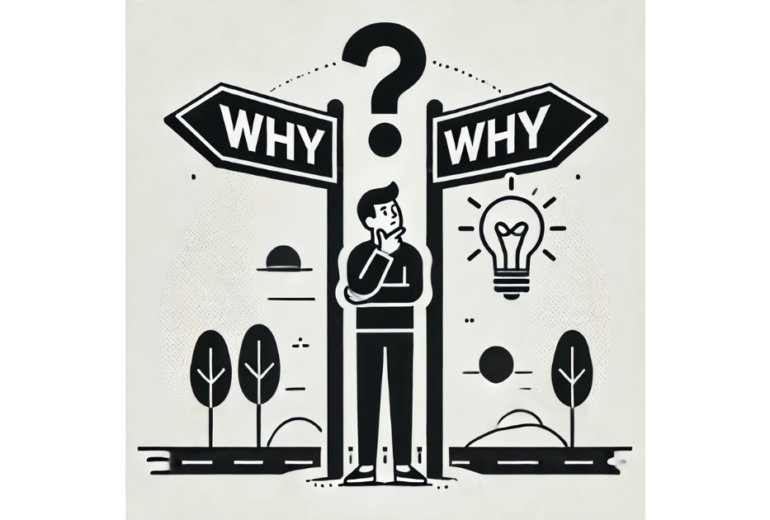


コメント