私たちはこれまで、視点を切り替えること、見方そのものを問い直すこと、そして関係性や場を耕すことの大切さを見つめてきました。
今回はもう一歩踏み込んで、「感性」というテーマに向き合ってみたいと思います。
「言葉にはできないけれど、確かに“ある”と感じる何か」
「数値では測れないけれど、まちの空気を左右しているもの」
それをどう捉え、どう扱い、どう活かしていけるのか。まちづくりにおいて“感性”を手がかりにするとは、どういうことなのか・・
今回は、その問いに具体的に向き合ってみます。
「なんとなく」の感覚を、手がかりにする
- なぜかこのまちは居心地がいい
- どうしてか発言が続かないワークショップ
- 目に見える活動は多いのに、どこか空虚さがある
こうした感覚は、「評価」や「分析」ではこぼれ落ちてしまいがちです。でも、だからこそ、それを“感じたこと”として置いておく文化が必要だと思うのです。
ポイントは、「感性をすぐ言語化・数値化しようとしないこと」。まずはそれを可視化せずとも“共有”することから始めてみるのです。
「合理性」だけでは、まちは読みきれない
もちろん、数値化やデータ分析、定量評価が不要だというわけではありません。行政や政策にとって「客観的根拠」は不可欠ですし、ロジカルな整理は意思決定の基盤でもあります。
けれど、合理性に軸足を置きすぎたまちづくりが、ときに「人の感情」や「場の空気」を置き去りにしてしまうこともまた、私たちは現場で実感してきました。
- 声は拾われているのに、納得されていない
- 計画は優れているのに、誰も“自分ごと”にできていない
- 成果は出ているはずなのに、継続しない、根づかない
その“違和感”の正体は、もしかしたら、数値ではとらえきれない“場の感性”を見落としているからかもしれません。
合理的であることは大切です。
でも、“それだけでは見えないものがある”ということを受け入れること。
そして、その“見えないもの”に耳をすます力を育てること。
まちをほんとうに持続可能にするためには、そんな「感性と合理性の往復」が必要なのだと、私たちは思っています。
感性を扱う方法①:違和感を“記録”する
「何かひっかかった」「ちょっとズレてる感じがした」・・そうした感覚を、打ち合わせや対話のなかで“書き留めておく”こと。
とくにこんなときに効果的です:
- プロジェクトのキックオフ時
- 関係性に緊張感があるとき
- 意見が表面的にまとまってしまったとき
◎ポイント:
- 「何がどうズレているかまでは分からないけれど…」という“あいまいなままの声”を拾っておく
- あとでチームで読み返すと、言語化される前の“本音”が浮かび上がる
感性を扱う方法②:“風通し”や“余白”の質を観察する
- 誰が発言しているか、していないか
- 沈黙が“気まずい”か“考える時間”になっているか
- 会議後の雑談が生まれているかどうか
こうした「関係の質の変化」をチェックすることは、まちやプロジェクトの“気温・湿度”を測るようなもの。
それは定量的ではないけれど、確実な「兆し」です。
◎たとえば:
「ミーティングの前後に雑談が生まれているか」
「沈黙のあと、誰かが安心して話し始められているか」
→ こうした小さな観察は、“場の質”のバロメーターになります。
感性を扱う方法③:まちの“音”や“気配”を記述する
私たちが現場を歩くとき、大切にしているのはこうしたことです:
- どんな音が聞こえていたか
- 誰と誰がどんなふうに立っていたか
- 外の風景と室内の空気のつながりはどうだったか
- 子どもが自由に動けていたかどうか
これは「まちを五感で記述する」営みです。数値ではなく、“ナラティブ”(物語)としてまちを記録すること。
そしてその物語が、まちづくりに「体温」や「奥行き」を与えてくれます。
「なんとなく」を見逃さない
違和感や空気の変化、居心地の良さや悪さ・・それらは多くの場合、「なんとなく」というかたちで私たちに現れます。
けれど、この“なんとなく”は、まちの奥行きを読み解く大事な手がかりです。はっきり言葉にできないからこそ、流されやすく、置き去りにされやすい。でも実はそこにこそ、“まだ言語化されていない課題”や“育ちつつある可能性”が潜んでいることが多いのです。
だからこそ私たちは、「なんとなく気になること」「なんとなくしっくりこないこと」を見逃さずに拾っておく。
それは、まちの“体温”や“風向き”を知るための、大切な感覚なのだと思います。
「感性 × 複数の視点」で“共有可能な手がかり”に変える
感性は主観的だからこそ、それを一人で抱えると「気のせいかな…」で終わってしまいがちです。
でも、複数の人が感性で捉えたことを持ち寄ると、共通点が浮かび上がってきます。
ひとりだけじゃなく、何人かが「なんか引っかかる」と感じたら、そこにはたいてい理由があります。
逆に、「あの場、なんだか心地よかったね」と感じた人が複数いるとき、そこには自然と共有されていた“何か”があるものです。これが、「感性を共有可能な判断軸」にしていく方法です。
“数値化しない判断軸”を育てる
私たちは、まちづくりにおいて「数字で語れること」も、「語れないけど確かにあること」も、どちらも大切にしたい。そして、「語れないけど確かにあること」も、記録し、共有し、観察することで、
“数値化しないけれど判断のよりどころになる”感性の基準を育てていけるのではないかと考えています。
それはきっと、“気配に気づく力”であり、“関係性の空気を読む力”であり、そしてなにより、「感じたことを、大事に扱える文化」のことです。
次回予告「時間軸でまちをとらえる視点」へ
次回は、時間の流れという視点からまちを見ていきます。歴史や記憶、継承といった「時間の地層」が、私たちの暮らしにどんな影響を与えているのか。瞬間ではなく、継続のなかで見えてくるまちの輪郭を考えてみたいと思います。











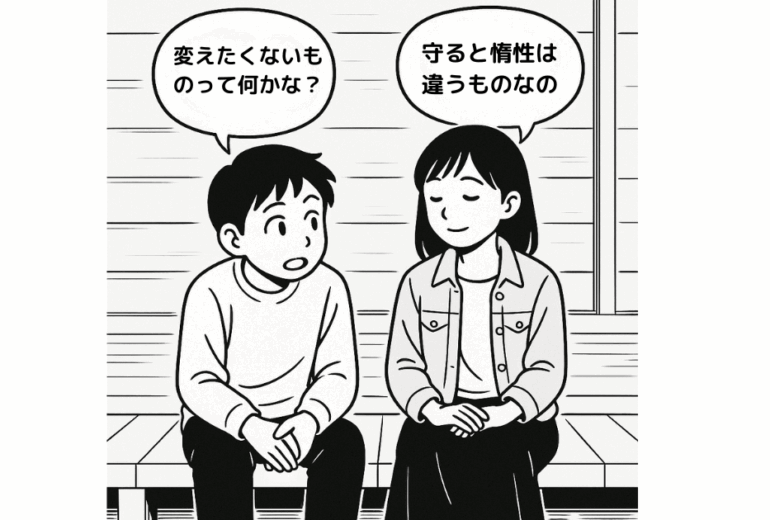

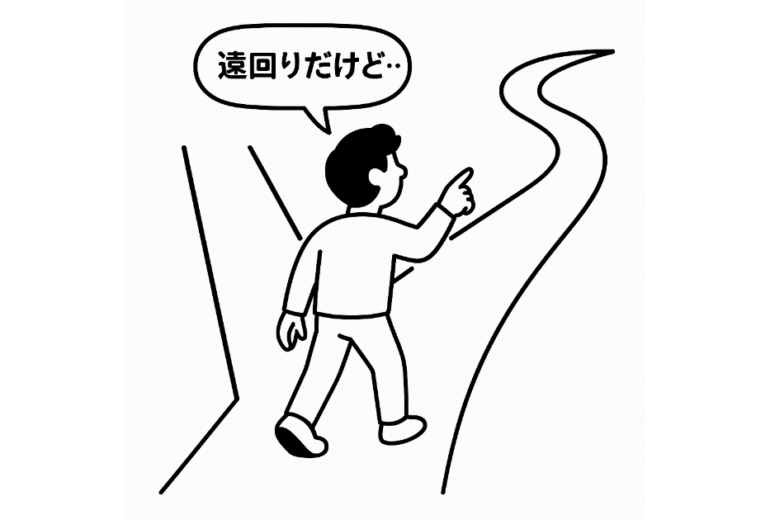


コメント