これまで私たちは、まちづくりにおいて大切な「視点」について考えてきました。
木を見て、森を見て、さらにその周囲を見わたし、問いの立て方を見直し、問いを育てる「対話と場づくり」の大切さにも触れてきました。
そうした探究のなかで、私たちの中にふつふつと立ち上がってきた問いがあります。
「そもそも、“まち”って、なんだろう?」
地図にのっている“地名”でもなく、制度としての“自治体”でもなく、あるいは建物やインフラの“集合体”でもなく。
もしかしたらまちは、「関係性の束」そのものなのではないか。
今回は、そんな視点から「まちを見る」という試みです。
「まち」を場所として見ると、見落とすもの
私たちはつい、まちを「地理的な空間」や「物理的なインフラ」として捉えてしまいがちです。
- まちの人口
- 商店街のにぎわい
- 公共施設の数
- 交通網や住宅地の分布
もちろん、これらはとても大切な要素です。でも、それだけでは見えてこない“空気”のようなものが、まちにはある気がします。
たとえば・・
- なぜこの集落は、あたたかく迎えてくれるのか
- なぜここの住民運動は、行政との信頼関係をつくれているのか
- なぜこの自治体では、若者の参加が自然と生まれているのか
それらの答えは、「物理的な構造」ではなく、「人と人との関係性」に宿っているように思えるのです。
まちは、見えない“関係の網の目”でできている
まちを「関係性」として見ると、いろんな風景が変わって見えてきます。
- 隣近所との距離感
- 行政と住民の信頼度
- 世代をこえた接点の有無
- 外から来た人が参加しやすい雰囲気
- 声をあげたときに“拾ってくれる”人がいるかどうか
これらは、地図にも統計にもなかなかあらわれない“まちの質感”です。
私たちは、まちづくりというと「物をつくる」「制度を変える」ことに注目しがちですが、それと同じくらい、「関係性を編み直す」「関係のなかで問いを耕す」ことも、まちをかたちづくる営みではないでしょうか。
関係性を「編む」「耕す」「ほどく」
関係性というと、しばしば「つなぐ」「広げる」といった言葉で語られますが、
私たちはむしろ「編む」「耕す」「ときにはほどく」といった行為を含めた方が、しっくりきます。
- 断絶があるところには、細い糸を通してみる
- 固く結ばれすぎたところは、ほどいて風を通してみる
- 土壌が痩せているところには、水と対話をまいてみる
関係性を手で触れるように扱い、丁寧に編み直していくこと。
それこそが「まちに関わる」という営みの本質なのではないか・・そんなふうに感じることが増えてきました。
関係性としての「まち」に向き合うために
では、「関係性としてのまち」に向き合うために、私たちは何ができるでしょうか。
たとえば・・
- “関係性の地図”を描いてみる
- 名前のついていないつながりに耳をすませる
- 過去の出来事や“共にいた時間”を記憶として語り継ぐ
- 誰がどこで「安心して話せているか/いないか」を観察する
- 立場を越えて関われる“第三の場”を用意してみる
関係は、空間を満たす“目に見えない風”のようなもの。でも、だからこそ、その風を感じ、整える感受性を持ちたいと思うのです。
まちは、関係でできている
まちとは、「人が集まっている場所」ではなく、「人と人とが関わっている状態」そのものなのかもしれません。
今まで、このシリーズでは構造を見て、制度を見て、場づくりなども考えてきました。そのなかで見えてきたのは、結局のところ「まちは関係である」ということ。
そして、その関係性をどうひらき、問い、育てていくかが、これからのまちづくりのカギになるのだと感じています。
次回予告「感性としてのまちづくり」へ
次回は、「感性」という視点から、まちづくりを見つめてみたいと思います。
論理や制度だけではなく、「なんとなく気になる」「どうにも気になる」という“感じる力”が、実はすごく大切なのでは?
そんな問いから、次の扉をひらいてみたいと思います。









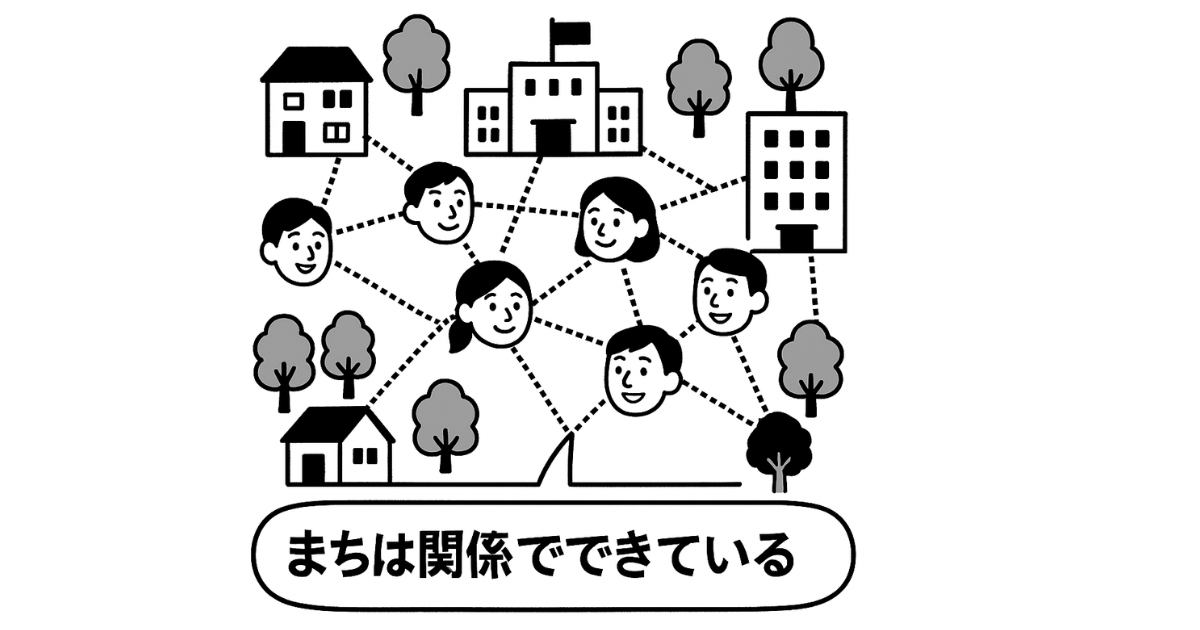







コメント