これまで、「木を見て、森を見る」ことの大切さを考えてきました。さらに、構造や制度の外側「森の周囲」まで視野を広げることで、自分たちの見方そのものを見直す“メタ認知”という視点に触れてきました。では、そのうえで、私たちはどんな問いを立てていけるのか?
今回のテーマは、「問いのデザイン」です。
なぜ、問いが大事なのか?
私たちが社会の課題と向き合うとき、何よりも先に立ち上がるのは「問い」です。
- これは誰にとっての課題なのか?
- 本当に“それ”が問題なのか?
- 見えていない前提はないか?
- そもそも、この状況にどんな意味を与えるべきなのか?
問いは、ただ答えを探すための出発点ではありません。問いの立て方そのものが、見えてくる風景をつくってしまう。だからこそ、「問いをどう立てるか」は、私たちのまちづくりや学び、行動のすべてに深く関わっているのです。
「いい問い」は、ちょっとざらついている
私たちの実感として、“いい問い”には、こんな特徴があります。
- 一瞬で答えが出ない
- 正解がひとつではない
- 立場によって見え方が変わる
- 自分自身をも巻き込む
- 問いを持ち続けることで、風景が変わってくる
たとえば、
「なぜ若者が来ないのか?」ではなく、「ここに来たくなる『理由』は、そもそも誰の視点で考えられてきたのか?」
「どうすれば空き家を活用できるか?」ではなく、「“家”という存在が、今どんな意味を持っているのか?」
問いのレベルを少しずらしてみるだけで、見える風景は大きく変わっていきます。
問いを立て直すことで、構図が変わる
たとえば、地域でよく出会う問いに、「どうすれば人が戻ってくるか?」というものがあります。
でもこの問い、どこか「戻るのが前提」になっていないでしょうか?
問いを少し立て直してみると、視野が広がります。
「人が減っていくなかで、どうすれば希望を育てられるか?」
「“豊かさ”の定義を変えたとき、地域の未来はどう見えてくるか?」
「ここで生きることを選ぶ人にとって、何が“しっくりくる”暮らしなのか?」
問いを変えると、関係性が変わり、見えてくる課題も変わり、行動の選択肢そのものが変わってきます。
デザインするとは、“配置しなおす”こと
「問いのデザイン」とは、別の言い方をすれば、すでにある関係性・前提・価値観を、一度「配置しなおしてみる」ということ。
- 誰が、何を、どういう前提で見ていたのか?
- 見えなくなっていた存在はなかったか?
- ことばの使い方が、視野を狭めていなかったか?
まちづくりも、教育も、ケアも、制度設計も・・実はこの「問いの設計」によって、全体の構図が変わってしまうことがあります。問いを整えることで、参加する人が増えたり、分断がやわらいだり、希望がにじみ出たりする。
それが、「問いの力」なんだと思います。
問いは、動き出すための“余白”をつくる
問いは、「正解を見つけるための道具」ではありません。それよりも、「もう少し考えてみようかな」と思える“余白”を生み出すもの。
まちのことを一緒に考える時間も、子どもたちと向き合う教育の場面も、日々の実践の中でつまずいたときも。
「問い直す」ことで、もう一度、目の前の風景を見つめなおすことができる。そのための“ことばの再配置”こそが、「問いのデザイン」なんだと思っています。
次回予告:問いを「開く」対話のつくり方へ
次回は、この「問い」をどう“ひらいていくか”。つまり、「問いを中心に据えた対話のデザイン」について考えてみたいと思います。
ひとつの問いを囲みながら、立場の違う人と話してみる。わからないままに問いを置いておく。それぞれが持つ“見え方の違い”を確かめあう。
そんな、思考と関係性のあいだにある「場づくり」の話に、少し踏み込んでみたいと思います。











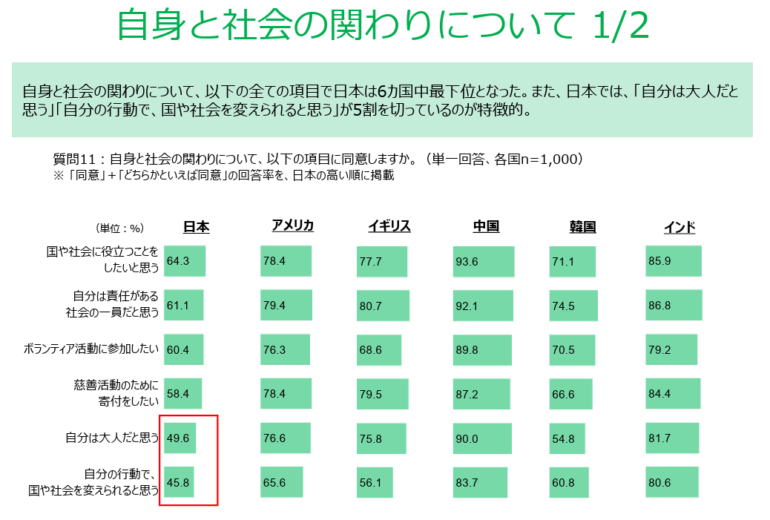


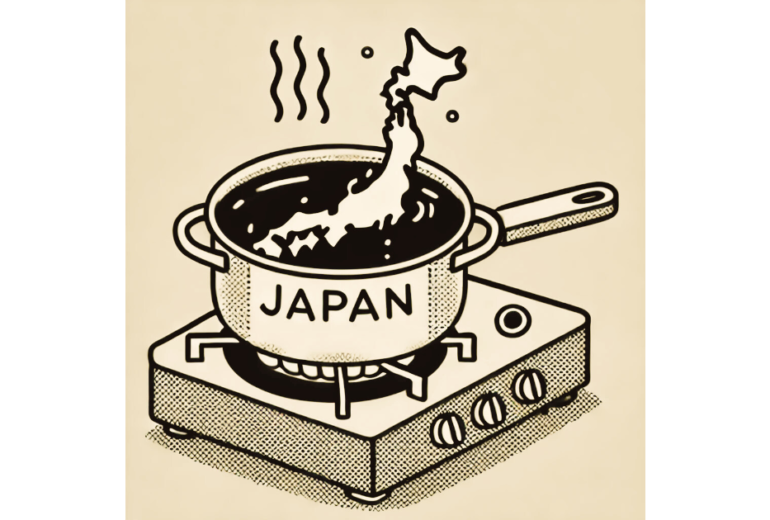


コメント