「説明は尽くした」「ワークショップも開いた」・・それでも納得してもらえない。合意には至らない。合意しても不満が残る。
こんな話、最近多くないですか。地域の一員として話し合いの場に立ち続けてきた人は不満がたまり、一方で、首長や行政職員、議員などはこう思うのです。
なぜ、うまくいかないんだろう。対話はしているはずなのに。
この問いを突きつけられるたびに思うのは、「やり方」以前に、「あり方」の問題なのかもしれない、ということです。
「やっている感」の正体
今の地域づくりには、「住民参加」という言葉がつきものになっています。説明会やワークショップ、アンケート、パブリックコメント、形式としての「参加」は用意されている。でも、それが住民にとって本当に意味のある時間になっているかというと、そうとは言い切れません。
「決まったことを説明されるだけだった」とか、「声を出したけど、どうせ何も変わらない」とか・・
そんな声が聞こえてくる場面が、あまりにも多い。つまり、“やっている感”だけが残って、関係も信頼も育っていない。実は、この「やっている感」、この問題に限らず、日本の生産性の低さなどにも関係しています。この関連については、また別の機会にお話しします。
合意を難しくしている、5つの社会構造
合意形成がうまくいかないのは、個人の努力不足やスキルの問題だけではありません。社会全体の構造が、そもそも合意を難しくしているのです。つまり、次のような5つの社会構造が複雑に絡み合って、合意形成を難しくしているのではないかと考えています。
1. 情報の非対称性
行政は背景・制度・予算・法律をふまえて提案します。でも、住民はその全体像を知らされないまま、判断を求められる。これでは対話になりません。
2. 制度の形骸化
参加の仕組みは整っているのに、それが「聞いたふり」「手続きのため」に使われている。声が最終決定に反映されないと、制度そのものへの信頼が薄れていきます。
3. 社会的信頼の偏り
日本の地域社会は「顔が見える関係性」で成り立っています。けれど、それが外から来た人や新しい声を排除する空気にもなってしまう。どうしても「有力者」の声を聴きがちです。
4. メディア環境の分断
SNSの発達で、自分に都合のいい情報だけに囲まれてしまう時代。「共通の現実」が失われ、対話の前提が壊れてしまっています。わかりやすい説を鵜呑みにしてしまうのです。
5. 合意形成の“コスト”の上昇
対話を丁寧に重ねようにも、行政には人手も時間も足りない。成果を急ぐ空気の中で、ゆっくり話すこと自体が困難になっているのが現実です。
制度から民主主義をつくり直す
「なぜ住民が合意してくれないのか」ではなく、「なぜ合意したくなるような制度や関係をつくれていないのか」と問い直す必要があるのだと思います。現代は「自己決定しているつもりになっている社会」で、選んでいるようで実は選択肢がなくて選ばされている、そんな状況に、私たちは慣れてしまっているのかもしれません。
本当の民主主義って、選択肢を「選ぶ」ことじゃなくて、選択肢を「共につくる」ことなんじゃないでしょうか。それを実現するためには、こんな取り組みがヒントになるはずです。
- 無作為抽出の市民討議会
- 市民参加型予算
- 合意形成のルールそのものを共につくるワークショップ
全国で少しずつ、こうしたチャレンジが始まっています。
合意形成から「関係性形成」へ
ハンナ・アーレントは、「政治において様々な見解を持つ人々が一つの決定を下すことは本質的に困難である」という問題を、否定的に(=だから決断が必要)捉えるのではなく、肯定的に(=それこそが人間の尊厳であり、政治の出発点である)と受けとめました。多様な意見や価値観がぶつかり合い、簡単に結論が出せない、だからこそ、共に悩み、対話しながら決めていくというプロセスに、政治の本質がある。そう考えると、合意形成の難しさそのものが、むしろ民主主義の核心を照らしているのかもしれません。
政治って、「共に決めるための関係性」をつくる営みのはずなのです。「説明したから納得するはず」と構えるのではなく、「なぜ納得できなかったのか」を問い直す。その姿勢からしか、新しい関係は生まれません。合意形成とは、正解を出すことではなく、わからなさに一緒にとどまって考え続けること。それができる制度と文化を育てることが、いま本当に求められているのだと思います。
遠回りに見えるけれど、”ひいては”その先にしか、本物の合意も、持続可能な自治も、きっとない。
問いを変えてみる。
「どうすれば合意できるか」ではなく、「どうすれば、合意を試みたくなる関係と制度を育てられるか」へ。
私たちはその問いを、これからも現場で持ち続けていきたいと思います。












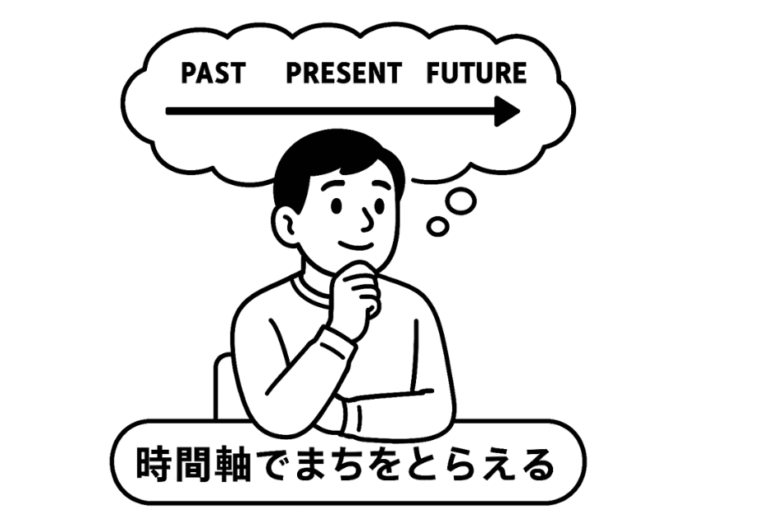

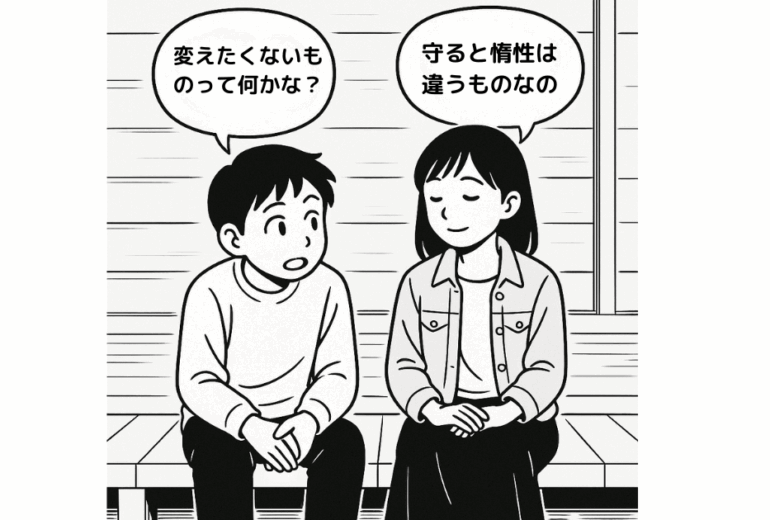



コメント