まちづくりの現場にいると、ときどきこんな場面に出会います。
「昔からこうやってきたんだから、変えるわけにはいかない」
「でも、このままじゃ続かないよ……」
“変えたくないもの”がある。けれど、“変えなければならない”こともある。そのはざまで、人びとは悩みながら、選択を重ねています。
けれどこの問いは、実は地域に限られたものではありません。むしろ、現代社会全体がいま、同じような問いに直面しているように感じます。
世界もまた、「変えたくないもののために変わる」局面にある
今、私たちの社会は、次のような大きな曲がり角に立たされています。
- 成長を前提とした資本主義の仕組みが、気候危機や格差の拡大を加速させている
- 人口減少が、制度や地域の持続可能性を根本から揺るがしている
- 消費と利便性だけでは、人の幸福を支えきれなくなってきている
これまでの社会の仕組みをそのまま続けても、もう立ち行かない。
現状維持では衰退していくばかり──そんな実感を、多くの人がうっすらと持ち始めているのではないでしょうか。
このことは、まちづくりにも深くつながっています。
エドマンド・バークという思想家のまなざし
こうした転換点において、今あらためて思い出したいのが、18世紀のイギリスの思想家、エドマンド・バークの考え方です。彼は、フランス革命を批判的に論じた著作『フランス革命の省察』(1790年)で、次のような言葉を残しました。
「社会とは、生者・死者・そしてこれから生まれてくる者たちとの契約である」
この言葉は、革命によって“すべてを刷新しようとする態度”に警鐘を鳴らすものでした。
バークは、「理性だけを頼りに、過去をすべて否定し、ゼロから社会を設計しようとすること」は危険だと考えたのです。
彼が重視したのは、制度や伝統のなかに込められた「非言語的な知恵」でした。つまり、それが長く受け継がれてきたということ自体に、ある種の合理性や適応力があるという前提に立っていたのです。
しかし一方で、バークは単に「伝統を守れ」と言っていたわけではありません。
彼が本当に伝えたかったのは、「継続性のある変化」こそが、社会の安定と自由を両立させる」ということでした。
保守とは、変化を否定することではない
“保守”という言葉は、ともすれば「何も変えたくない」という印象で捉えられがちです。けれど、バークの考えに触れると、それがまったくの誤解であることがわかります。
彼の保守思想とは、過去の知恵や関係性を大切にしながら、状況に応じて調整し、更新し、未来につないでいくための“態度”のこと。
変えたくないものを守るためには、変えなければならないものがある。
そうした逆説に耐える構えこそが、真の保守だとバークは語っていたのです。
まちの中にもある、“しなやかな保守”
このバークのまなざしは、地方のまちづくりの現場でも、ふとした瞬間に姿を見せます。
- 高齢化で担い手が減った伝統行事を、若い世代が“今のやり方”で再解釈し直す
- 空き家になった家を、地域の居場所や新しい仕事場として使いなおす
- 昔ながらの祭りに、親子で参加できるような工夫を取り入れる
これらはすべて、「残したい思い」を未来へつなげるための変化です。形式にしがみつくのではなく、「何を大切にしてきたのか?」という問いを軸に、かたちを編みなおしていく。
これこそが、“しなやかな保守”の実践ではないかと思います。
過去に学ぶとは、過去に縛られることではない
過去を大切にすることと、過去に拘泥することは、まったく違います。
「これまでやってきたから」という理由だけで守るのではなく、「なぜそれを残すべきなのか?」という問いに、誠実に向き合う。そこで初めて、“守るに値するもの”が浮かび上がってくる。
逆に、問いを立てずに形式だけを守っても、それは継承ではなく、やがて形骸化していくだけなのです。
続けるために、変わる
「守るとは、変えないことではない。」
この逆説的なまなざしは、まちを持続させるためにも、社会を再構築するためにも、今、あらためて必要とされているのだと思います。これからの時代に必要なのは、過去を見つめ、未来に責任を持ち、いまを問い直す“変化の構え”なのかもしれません。
次回は、「まちを守るために、問い続ける」というテーマで、継承と刷新の分かれ道に立つとき、どんな視点が必要なのかを一緒に考えてみたいと思います。















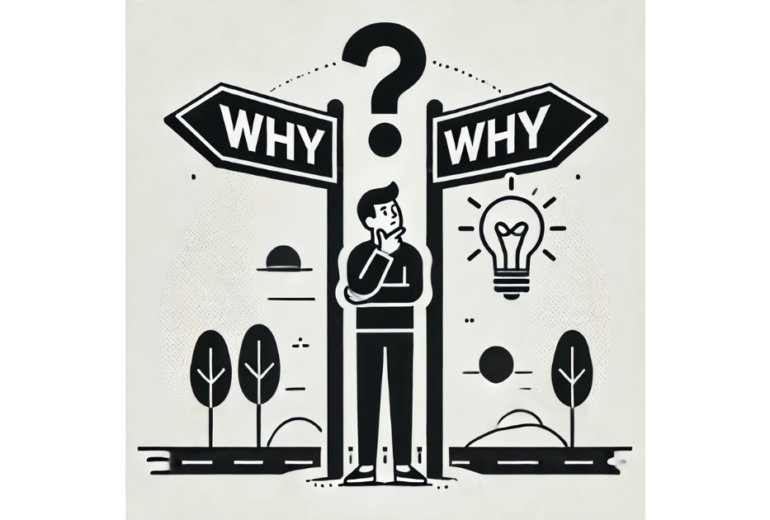


コメント