「失われた30年」。この言葉を聞くと、バブル崩壊から続く日本の停滞感を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。けれど、その言葉だけでは語りきれない希望も、課題も、日本のあちこちに転がっています。実質賃金の低迷、物価の上昇、産業構造の変化。もちろん、それらは現実です。でも一方で、「日本の生産性は本当にそんなに低いのか?」という視点も必要です。実は、経済協力開発機構(OECD)のデータでは、2021~2023年の時間当たり労働生産性の伸び率は日本が1.5%増で、欧州主要国よりも堅調でした。10年間の平均でも、ドイツやフランスと肩を並べる水準にあります。
では、なぜ「停滞感」が強いのでしょうか。その答えは、数字だけでは見えてこない、働き方や暮らし方、制度や価値観にあるのかもしれません。制度の整備や政策の転換ももちろん重要ですが、それと同じくらい —いや、もしかするとそれ以上に— 私たち一人ひとりの「意識の変化」「行動の変化」が、未来を変える鍵になるのではないでしょうか。
ここでは、これからの地域・社会のあり方を考えるための8つの視点をご紹介します。
①働き方を見直す―「みんな一緒」から「自分らしく」へ
日本の雇用制度は、長く「メンバーシップ型」——つまり会社に合わせる働き方が中心でした。でも、いま求められているのは「ジョブ型」、自分の専門性を活かし、必要なときに、必要な場所で働ける柔軟性です。副業、リモートワーク、フリーランス。これらは一部の人の特権ではなく、誰もが自分らしく働ける社会への入り口です。
②家事・育児は「女性の仕事」じゃない―対話と役割の再構築
「男性の育休? 取れたらいいけど…」という声がまだまだ多いのが現状。でも、これは制度の問題だけでなく、私たち一人ひとりの意識の問題でもあります。家事や育児を「女性の責任」とするのではなく、「家族全体の暮らしをどう支え合うか」という視点に変えていくこと。それが、男女共同参画の本当の意味です。
③教育と探求が未来をつくる―AI時代の学びを地域から
私たちの社会は、今まさに大きく変わっています。AI、データ、グローバル経済・・こうした時代に必要なのは、単なる知識ではなく、「問いを立てる力」や「自分で考え、つながる力」です。そのために必要なのが、探求学習。学校や地域、企業が連携し、子どもたちや若者が「なぜ?」を出発点に、現実の課題に向き合いながら学べる場をつくることが、未来の生産性を支える土台になると信じています。
④多様な家族、多様なつながり―血縁だけじゃない「暮らしの共同体」
家族のかたちは、これからますます多様になっていきます。シングルペアレント、LGBTQ+カップル、友人同士の共同生活……どれも立派な「暮らし方」です。さらに最近では、血縁を越えた地域の仲間たちとのコミュニティづくりが注目されています。たとえば、シェアハウスや共助ネットワーク。これらは単なる生活の手段ではなく、「誰かとつながりながら生きる」選択肢でもあります。
⑤デジタルを“手段”に―人と人をつなぐ技術の活用
デジタル化は、効率化のためだけのものではありません。むしろ、遠くの人ともつながれる、情報を共有できる、声を可視化できる。そんな「人をつなぐ技術」として捉えることで、地域の可能性は大きく広がります。行政の手続きも、教育の場も、デジタルがあればもっと柔軟に、もっと開かれたものになる。大切なのは「技術」よりも、それをどう「使うか」です。
⑥イノベーションは「正解探し」ではなく「共創」から
イノベーションというと、何か特別な技術や発明のように思えますが、本当は「新しい組み合わせ」でしかありません。たとえば、地域の伝統と現代のアイデアを組み合わせること。高齢者と若者が一緒に何かを始めること。そんな「人と人との化学反応」こそが、イノベーションの種なのです。
⑦幸せを測るものさしを変えよう―ウェルビーイングの視点から
経済成長も大切ですが、それだけでは見えないものがあります。「どれだけ稼いだか」よりも、「どれだけ心地よく暮らせるか」。ワークライフバランス、居場所のある暮らし、健康、自然との関わり—そうした視点を「豊かさ」として認める社会へ。これは、行政や企業にとっても新しい評価軸になるはずです。
⑧グローバルからローカルへ―足元から変える経済のかたち
グローバル経済の恩恵を受けつつも、これからは「足元」に目を向ける時代です。地域資源を活かしたビジネス、地元の人たちとつくる観光、農業、教育……。こうした「地に足のついた経済」は、決して規模は大きくなくても、持続可能で、人を幸せにします。
「失われた30年」という言葉の先にあるのは、「これからの10年」です。その10年をどう過ごすかで、地域も社会も、そして私たち自身の暮らしも変わっていきます。もちろん、国の様々な仕組みや制度が時代に合っていないことは間違いなく、それを変えることも大切です。けれど、その制度をどう受け止め、どう活かすかは、私たち次第です。
私たち一人ひとりが、「こうなったらいいな」と思うことを、声にし、行動にし、小さなチャレンジを積み重ねていくことで、あの“失われた30年”さえ、学びと再生の時間に変えていけるかもしれません。変化は、決して上から降ってくるものではありません。私たちの毎日の選択が、未来の景色を少しずつ変えていくのです。










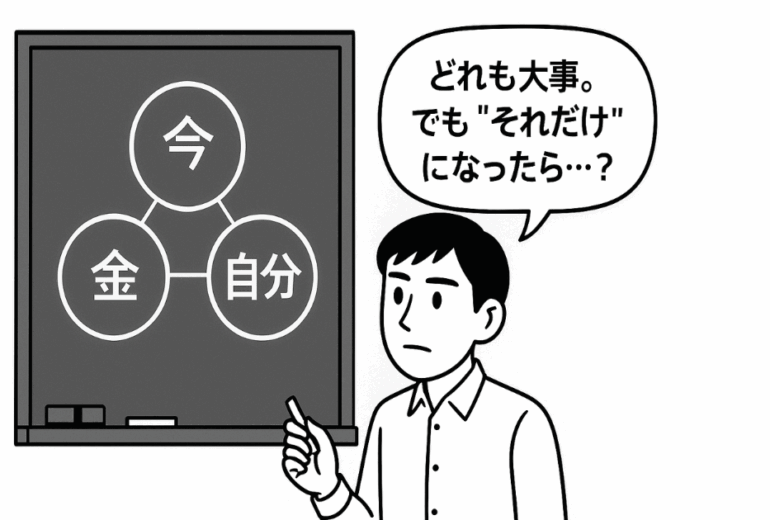
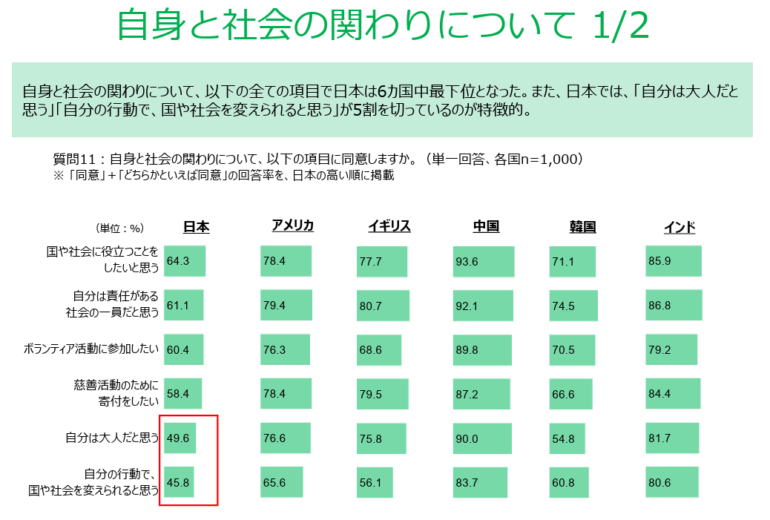
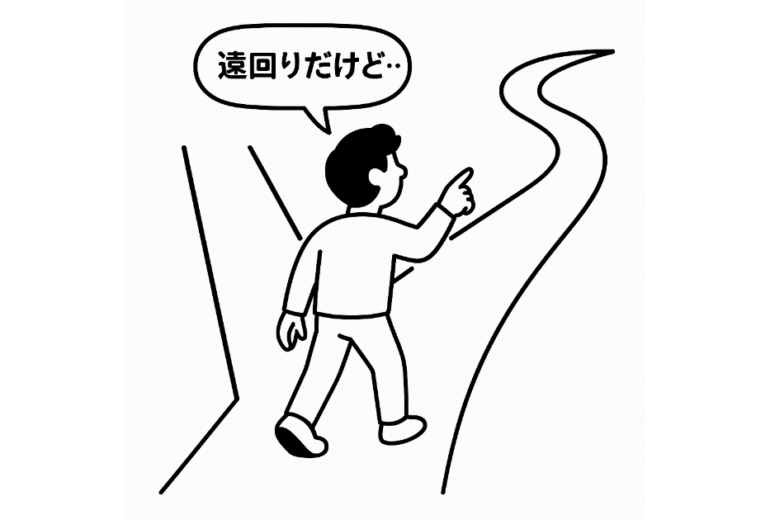




コメント