私たちが直面する最大の課題「人口減少」がもたらす諸課題は、一朝一夕で解決することが難しいものばかりです。つい目先の成果を求めたくなることもありますが、そうしたときこそ思い出したいのが、孫子の兵法にある「迂直の計」という考え方です。
これは、あえて遠回りに見える道を選ぶことで、結果として最短の成果を得るという戦略。
日本にも、これと同じ意味を持つことわざが昔からあります。それは「急がば回れ」。
急いでいるときこそ、慌てて危険な近道を選ぶよりも、安全で確実な遠回りを選ぶほうが、結局は早く目的にたどり着ける。古くから伝わるこの知恵は、今の私たちにも深く響きます。
そして、これらと並んで今、改めて意識したいのが「ひいては」という言葉です。
「ひいては」とは、直接的ではなくても、まわりまわって最終的に物事に影響を与えること。
つまり、今行っている行動や取り組みが、すぐに成果につながるとは限らなくても、やがて大きな変化を生み出す可能性がある、そんな含みをもった言葉です。
地域づくりも、教育も、「ひいては」の営み
地域づくりも、教育も、まさにこの“ひいては”の世界にあります。
たとえば、地域課題に正面からアプローチしようとすると、「とにかく制度を変えよう」「今すぐ事業化しよう」といった直線的な解決策に走りがちです。
しかし、実際には住民との信頼関係づくりや、丁寧な合意形成、地域の文化や歴史への理解といった“見えづらい土台”を築くことこそが、持続的な変化の鍵になります。
それは、ひいては地域の自立や誇り、そして持続可能な未来につながっていくのです。
教育においても同じことが言えます。
知識を詰め込み、正解を早く出すことだけでは、これからの時代を生きる力は育ちません。
むしろ、失敗を経験しながら考え続けること、人と違う視点を持つこと、問いに対して自分なりの答えを見つけること、そうした一見“遠回り”に思える学びこそが、子どもたちに本当の力を与えてくれます。
すぐに成果として見えるものではなくても、それが“ひいては”社会を支える人材となり、地域や未来を育む土台となるのです。
地域に学びを、学びに地域を -その交差点の可能性-
そして、地域づくりと教育は、けっして別々のものではありません。
いま、地域の現場でも「教育の力」が求められています。
地域をフィールドにした探究学習や、住民との協働による課題解決型の学びは、子どもたちにとっての“生きた学び”となり、同時に地域に新しい視点と希望をもたらします。
一方で、教育の現場にとっても、「地域というリアルな場」は、教室では得られない深い学びを提供してくれます。
地域を知ることは、自分を知ることにつながり、やがて社会を変える力にもなる。
だからこそ、地域と教育が交わる場所には、大きな可能性があるのです。
方針さえ決まれば焦らなくていい。でも、立ち止まってはいけない。
私たちは、地域づくりも教育も、「今すぐ結果を出す」ことよりも、「続いていく関係性を育む」ことに重きを置きたいと思っています。遠回りに見えても、時間をかけて築いた信頼や経験こそが、未来の大きな資産になる。
そして、それは“ひいては”地域の力となり、未来を生きる子どもたちの背中を押してくれるはずです。
けれど、だからといって「時間がある」と油断していいわけではありません。
特に、人口減少が加速している地方にとって、これからの数年は決定的に重要な分岐点になる可能性が高いのです。このタイミングで何を選び、どんな道を歩むのか。
その判断が、未来の可能性を広げることもあれば、逆に閉じてしまうこともあります。今こそ、目先の成果にとらわれるのではなく、本当に大切な“土台”を築くことにエネルギーを注ぐべきときです。
まっすぐな道だけが正解じゃない。
むしろ、遠回りにこそ、景色があり、出会いがあり、気づきがあります。今の一歩が、どれだけ遠く見えても、それが「ひいては」、未来へと続く確かな道になる。
私たちは、その一歩を、丁寧に、でも確かに、踏み出したいと考えています。









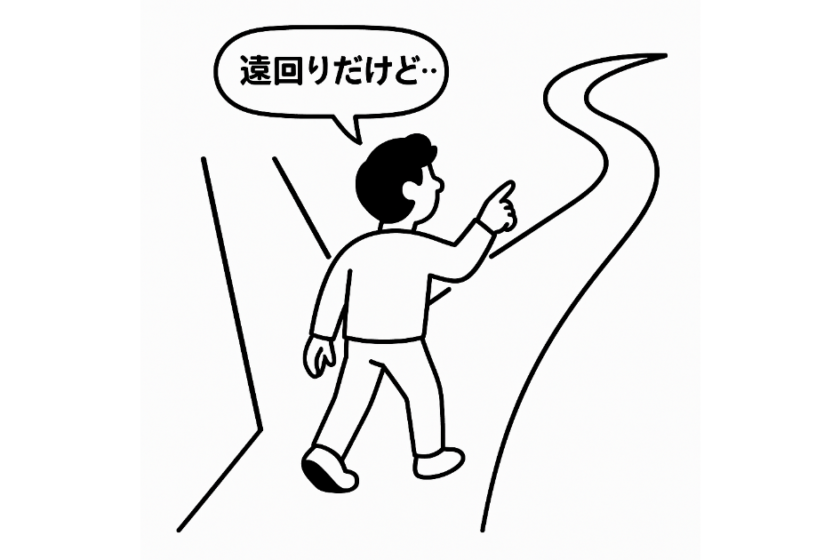




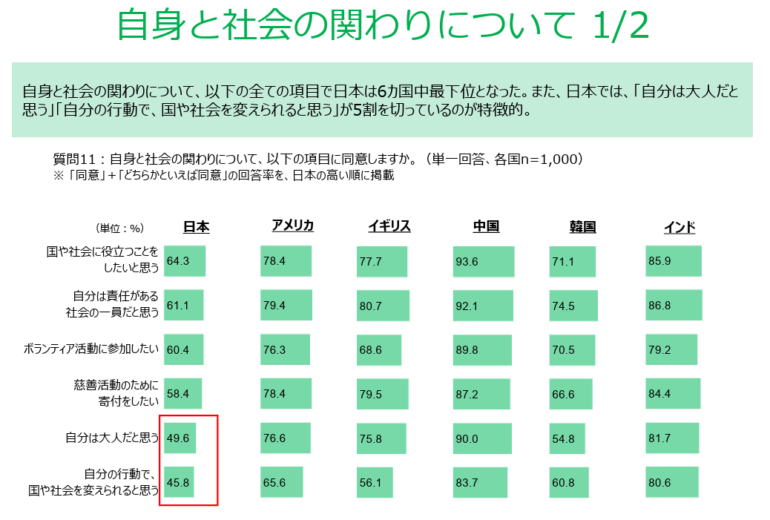


コメント