お盆が近づくと、街も人も、少しずつ「帰る」方向へと向き始めます。
駅は人であふれ、高速道路は渋滞し、スーパーの棚には家族を迎え入れる料理の食材が並びます。
日本の夏らしい風景ですが、これをSBNRの視点から眺めてみると、また違った輪郭が見えてきます。
「SBNR」とは、Spiritual But Not Religious。宗教的ではないけれど、精神的なものを大切にする生き方。
お盆は、必ずしも教義や宗派に従う必要があるものではありません。
それでも、多くの人がこの時期に感じる「誰かとのつながり」や「自分のルーツに触れる感覚」は、確かに存在します。
お盆とは何か?
お盆は、日本各地で毎年8月13日〜16日頃に行われる先祖供養の行事です。
仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)に由来し、先祖の霊がこの世に帰ってくると考えられています。
迎え火で霊を迎え、期間中は仏壇や墓前で供養し、送り火で再び送り出す、この一連の流れが基本です。
地域によっては盆踊りや灯籠流しが行われ、家族や親戚が集まる年中行事としても定着しています。
宗派や信仰の有無にかかわらず、多くの人が「先祖を思い、家族と過ごす時間」として受け止めており、現代では精神的な節目や帰省のきっかけとしての側面も強くなっています。
SBNRの視点から見れば、お盆は宗教儀式であると同時に、「目に見えないつながり」を意識する年に一度の時間でもあります。
時間をまたぐ感覚
お盆は、単なる夏休みのイベントではありません。遠くに暮らす家族や親戚と顔を合わせ、先祖の墓に手を合わせる。たとえ、それが宗教的信仰の一部でなくても、そこで過去と現在が、静かに一本の線で結び直されます。線香の煙が空にほどけていく様子を見つめながら、「自分はどこから来たのか」をふと思い出す。
それは、教義は関係ない静かで個人的な行いです。
お盆に伴う帰省も、単なる物理的な移動ではありません。自分を形づくった風景や匂い、人の声、それらに触れることで、忙しない日常で崩れがちな調子が少し整っていきます。都会で加速しすぎた日常を、一度アイドリングに戻す。親や親戚との他愛ない会話、地元の友人の変わらない笑顔。
そうした断片が、「自分にはまだ帰れる場所がある」と教えてくれます。
血縁者が少ない時代に
しかし、この構図は変わりつつあります。人口減少と都市集中の中で、「帰る先に血縁がいる」こと自体が、当たり前ではなくなってきました。
祖父母の家は空き家になり、親戚は県外に散らばる。帰省が“家族訪問”というより、“土地そのもの”や“地域との再会”になるケースが増えています。
SBNRの視点で見れば、これはつながりの再編成です。血のつながりに限らず、自分が安心できる人や場を“家族”と感じる・・そうした関係を自分で選び取り、育てていく時代になりました。
花火と人の輪
お盆の頃、株式会社4DeeRが拠点を置く池田町周辺では、夜空を彩る花火大会が続きます。8月13日は高瀬川、14日は安曇野、15日は木崎湖と、三夜連続で夏の夜を照らす光の祭典です。
帰省した家族と、自宅の庭から見上げる花火。浴衣姿で出かけた街角では、夜風に乗って届く笑い声。そして、夜空いっぱいに咲く大輪の光に響く歓声。それらが重なり合い、この土地の夏を記憶に刻んでいきます。
その輪の中には、血縁がある人もいれば、この土地に魅かれてやってきた人もいます。
宗派や背景が違っても、同じ時間と空間を共有する。
その中で生まれるのは、「私たちはここに生きている」という、確かな感覚です。
かんば焼き・・白樺の煙で先祖を迎える
長野県では、お盆の迎え火として「かんば焚き」という独特の風習があります。
白樺の樹皮を5センチほどに切り、火をつけると、油分を含んだ樹皮が黒い煙を立ちのぼらせます。
その香りや煙は、遠く離れた魂を導く道しるべのように、ゆっくりと空へと溶けていきます。
それは、宗派に関係なく、土地の人々が先祖を迎えるための儀式として受け継がれてきました。
SBNRの視点で見れば、これは宗教的枠組みを越えた精神文化の一形態。先祖からのつながりを感じるスピリチュアルな瞬間です。
海外から見たお盆の魅力
近年、日本を訪れる外国人の中にも、お盆に強い関心を持つ人が増えています。
彼らにとって、お盆は単なる宗教行事ではなく、“目に見えないものへの敬意”や“共同体の記憶”が可視化される時間として映ります。
灯籠流しや盆踊り、そして白樺の煙が夕方に立ちのぼる「かんば焼き」の光景は、SBNR的な価値観「宗教の枠を越えたスピリチュアルなつながり」と深く共鳴します。
特に、血縁が薄れても地域全体が「帰る場」を提供する姿は、多文化社会で生きる人々にも示唆的です。
“家族”を血のつながりだけで定義しないこの在り方は、国や文化を越えて共感を呼ぶものでしょう。
それぞれの“お盆”をデザインする
現代では、帰省できない人もいますし、慣習に距離を感じる人もいます。
それでも、SBNR的にお盆を過ごす方法はいくつもあります。
- 花や灯り、食事など、自分なりの迎え方をつくる
- 故人や大切な人の思い出を、家族や友人と語り合う
- 地域の行事に足を運び、人や土地とのつながりを感じる
- 実家でなくても、自分が「帰る」と思える場所を訪ねる
お盆は、単なる年中行事ではなく、人と人、時間と時間、そして心と場所を結び直す節目といえるでしょう。
血縁が薄れゆく時代だからこそ、地域で生まれる新たな「つながり」が、私たちの心を静かに支えてくれます。
その姿は、日本人にとってはもちろん、この国を訪れる外国人の目にも新鮮で魅力的に映ります。
日本の豊かな精神性を映し出し、SBNR的価値観を体現するお盆・・これから時代の変化とともに形が変わっても、その本質は大切にしていきたいものです。












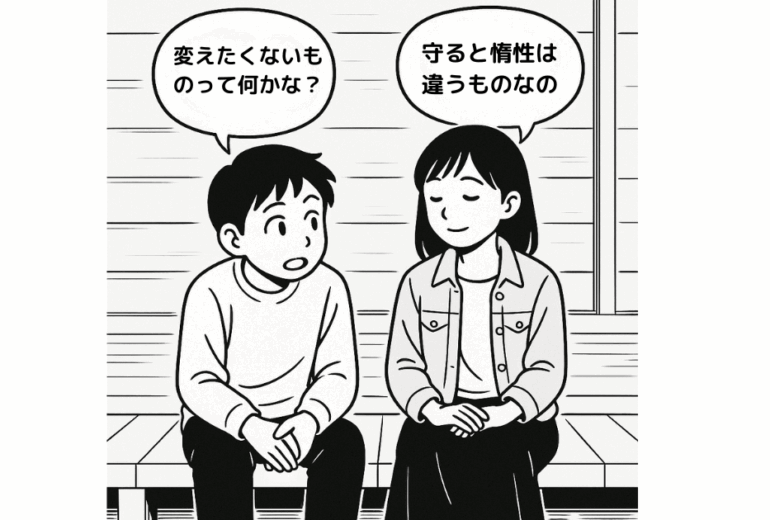

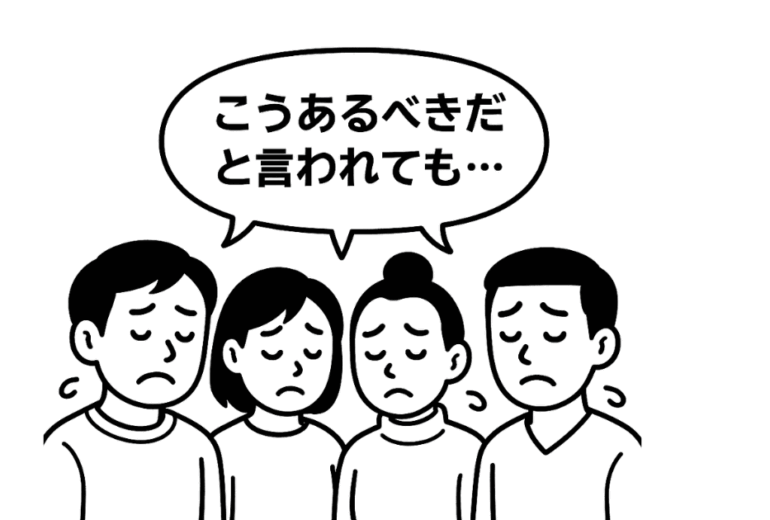


コメント